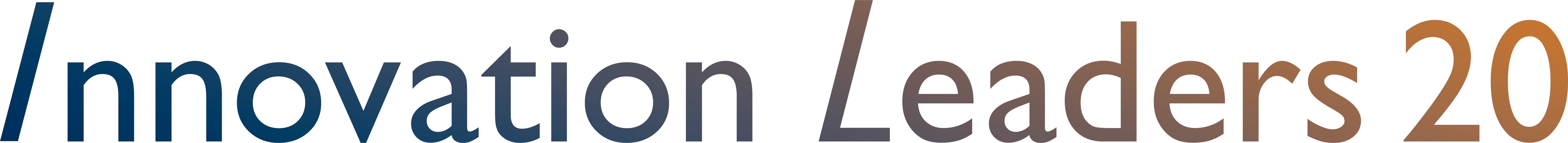セザール・リッツの哲学を体現する男
セザール・リッツは「お客様を王族のように迎えよ、そうすれば彼らは王族のように振る舞うだろう」と言った。彼はホテルという空間を単なる宿泊施設ではなく、夢を形にする場所へと変えた。豪華さや格式だけではなく、サービスという名の魔法をかけ、訪れる人々に記憶に残る時間を提供した。そんな彼の哲学を体現するかのように、青森県弘前市に一人の男がいる。
「僕は単なる料理人でした。」そう語るのはブロッサムホテル弘前の総支配人である福士圭介。彼は決して宿泊業に精通した家系で育ったわけでもない。ホテルマンとして教育を受けてきたわけでもない。彼の出発点は、むしろ料理の世界にあった。東京で懐石料理を学び、和食の道を極めるはずだった男なのである。
ホテルの舵を取る料理人
東京で懐石料理を学び、和食の道を極めるべく修行を積んできた福士代表。研ぎ澄まされた包丁さばき、食材の持つ本来の味を最大限に引き出す技術。彼は料理に没頭し、職人としての道を歩むはずだった。しかし、宿命は彼を予想外の方向へと導く。実家である福士旅館が都市計画の影響を受け、一時閉業を余儀なくされる。何世代にもわたり続いた旅館の灯を、絶やしてはならない。その思いが彼の中に強く芽生えた。
だが、ただ戻るだけでは意味がない。東京での修行を終えた彼はパレスホテルでの経験を通じて、一流のサービスとは何かを体得する。料理を超え、空間全体を演出し、訪れた客に特別な時間を提供する。そのすべてを吸収したのち、彼はついに決意する。「戻らなければならない。ただし、新しい形で。」
2000年、ブロッサムホテル弘前として新たなスタートを切る福士旅館と福士代表。だが、彼の試練はここから始まった。宿泊業の経験ゼロ、右も左も分からないまま、彼はホテルの舵を取ることになる。経営者として、料理人として、そして現場のスタッフとして。彼は手を汚すことを厭わない。フロントに立ち、ルームサービスを運び、清掃スタッフと共に汗を流す。ホテル業界の教科書には載っていない方法で、彼はまさしく「自分のホテル」をつくり上げたと言っても過言ではない。
ホテル経営は決して順風満帆ではなかった。特に東日本大震災の影響は甚大だったと彼は語る。観光客は激減し、売上は落ち込む。だが、福士代表は諦めなかった。むしろこの危機をチャンスと捉え、地域との連携を強めた。「シンプルですが、地域が潤えば、ホテルも潤うんです」そう話す彼の顔は確信に満ちていた。そしてコロナ禍。多くのホテルが閉鎖や人員整理を余儀なくされる中、福士代表は決断する。「誰一人解雇しない」…彼は行政と連携し、コロナ患者の受け入れ施設としてホテルを運営。結果として、従業員の雇用を守るだけでなく、地域医療の支援という新たな役割を果たすことになった。そしてコロナが落ち着いたタイミングでリニューアルを敢行。ピンチをチャンスに変える、その手腕こそが彼の真骨頂だろう。
仕掛けた独自戦略
現在、ブロッサムホテル弘前は青森・弘前における観光とビジネスの中心地として確固たる地位を築いている。全35室のホテルは、洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、訪れる客に「第二の我が家」と思わせるような温もりを提供する。外国人観光客の増加を見越し、多言語対応のスタッフを配置。ビジネス利用客には、高速Wi-Fiやワークスペースを完備した部屋を提供。EV充電設備、レンタサイクルの導入など、細部にまでこだわる。
特に彼がこだわったのは、ただの「宿泊施設」ではなく「オンリーワンサービス」を提供すること。大手ホテルが大量の客をさばくことに注力するならば、ブロッサムはあえてその対極をゆく。朝食はビュッフェではなく、ルームサービスでご提供。ゆっくりと起き上がり、寝ぼけ眼のまま美味しい朝食を楽しむ。化粧や身だしなみを整える必要もない。客のプライベートな時間を最大限に尊重し、その快適さを徹底的に追求する。福士代表は時代の流れを的確に読み取り、弘前で評価される自分たちの得意分野がなにかを見極めてきたのだ。
「爆進型」スタイルで飛び込め
福士代表は「市場に合わせる」のではなく、「市場を創る」ことに全力を注いできた。客層を選び、ホテルの個性を際立たせる。バイキングスタイルが好きな人には、はっきりと他のホテルを薦める。「うちはこういうスタイルです」と明言する。結果、宿泊客の満足度は驚異的な数値を叩き出し、リピーターが増え続ける。まるでセザール・リッツが築いた高級ホテルのように、ブロッサムは独自のサービスを武器に、唯一無二のホテルへと成長した。
福士圭介は「爆進型」だと言う。思いついたことは即実行し、ダメならすぐに軌道修正する。その柔軟性と決断力こそが、彼のホテル経営を成功に導いた最大の要因だ。だがそれは単なる「猪突猛進」ではない。彼の根底には、幼い頃から育まれた「宿泊業の原点」がある。旅館業を営んでいた家に生まれ、お客様と日常を共にした経験。宿泊業は単なるビジネスではなく、人と人とのつながりそのもの。彼はそれを知っている。
この物語は、未来を担う若い世代にも響くはずだ。彼の生き様から学べることは多い。もし今、何をすればいいのかわからないなら、まずは「動いてみること」。福士自身、未経験の宿泊業界に飛び込み、試行錯誤を繰り返しながら成功を掴んだ。失敗を恐れず、自分の信じる道を突き進むこと。それこそが、新しい何かを生み出す第一歩になる。
そして、彼はこうも言う。「どんな人と出会うかで人生は変わる。だからこそ、興味を持ったことには躊躇せず飛び込んでみるべきだ。」と。新しい環境に身を置き、多様な価値観に触れることで、視野が広がり、自分の可能性に気づくことができる。福士圭介の物語は、挑戦と革新の連続だ。そしてその物語は、若い世代に対しても大きな示唆を与えている。何かを成し遂げたいと思うなら、まずは一歩を踏み出し、学び、行動し続けること。それが、未来を切り拓く鍵となる。