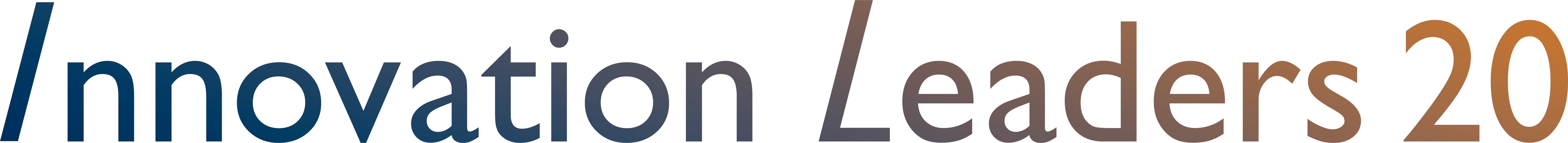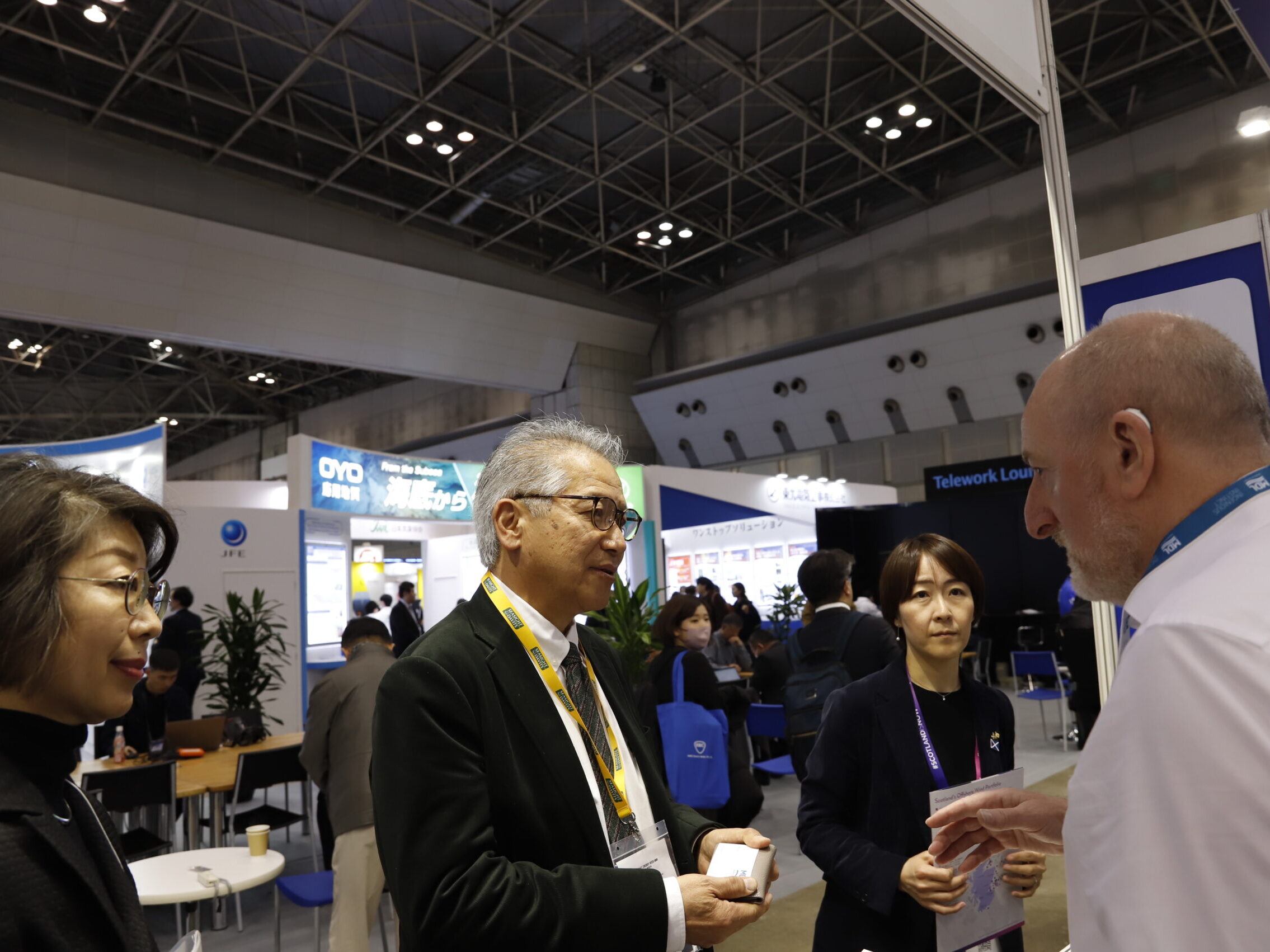積雪で苦しむ人々を救いたくて
時代が移り変わるとき、人々が見落としがちなものがある。それは土地に根ざした「本当の可能性」だ。
エネルギー産業の歴史を眺めると、常に巨額の資本と巨大設備が動かす華々しいイメージばかりが取り沙汰されるかもしれない。だが、その裏側には地域の気候・環境、地形、そこに暮らす人々のライフスタイルを巧みに活かし合う“在地型の技術革新”が、確かに存在してきた。現代では、大型化が進む風力発電や太陽光パネルの大規模設置がエネルギー転換の主流として叫ばれている。しかし、“地域の風”や“雪深い土地”ならではの課題に正面から向き合い、「この地で暮らす人を助けたい」という純粋な思いから事業を興す者もいる。株式会社アイアールエフ代表取締役・長谷川直宏は、まさにその一人だ。
株式会社アイアールエフは2013年12月に設立された。資本金1000万円、正社員3名に加え協力会社5社とタッグを組む。五所川原市を中心に、再生可能エネルギー機器の製造・販売・施工までワンストップで提供し、地域の人たちが無理なく利用できるよう懇切丁寧に解説している。農業・小規模な農地・一般の家庭でも導入できるよう、小型風力の仕組みを一から説明してくれるのだ。売電を通じて副収入が得られるケースだけでなく、近年は「自家発電を行い、地域の雪対策にまわす」アイデアを提示するなど、新しい再エネのカタチを追究している。まるで地元の“かかりつけ医”のように、技術と地元特有の環境をつなぎ、使う人がつまずきそうな問題を先回りして解決する。そんな姿勢こそが、この会社最大の強みだ。
アイアールエフの拠点は、青森の風と雪が荒々しく肌を刺す津軽地方。この地を拠点に、電気ヒーターの開発・製造、そして施工・メンテナンスまで一貫して行っている。冬になると凍りつく道路や駐車場、積雪による生活への影響に苦しむ人々を、どうにか助けたい…そんなモチベーションが同社の原点だという。しかも長谷川は小型風力発電の普及やメンテナンス事業にも打って出た。かつてヨーロッパのメーカーが提供していた小型風力発電機が次々と撤退・倒産を余儀なくされ、ユーザーが置き去りにされた状況をなんとかしようとフォローに回ったのがきっかけだ。誰かがやらねば人々が困る。ある意味では泥臭く、リスキーで、儲かるか分からない。しかし、その“おせっかい”とも呼べる行動が地元にとって何よりもありがたい。まさに古い価値観と新しい技術が織り交ざる“エネルギー産業の今”を、この青森から独自のアプローチで切り開きつつある。
アイデアはあるが、カネはない
だが、長谷川がここに至るまでの道のりは決して平坦ではない。そもそも近畿大学工学部(広島キャンパス)に進学し、経営工学を学んだ若き日から彼の人生は軽やかにジグザグを描いてきた。卒業後は青森リコーに就職するが、わずか3年ほどで独立を決意。まだ何者でもなく、資本もなく、技術を確立しているわけでもない。しかし「自分の思い通りの製品を設計・製造したい」という熱だけはあった。加えて青森の雪に悩まされる人々を救う策はないものか…その思いに突き動かされ、個人事業として電気ヒーターの開発・試験施工を始める。
当時は携帯電話もまだ今ほど普及しておらず、補助金制度なども整備されていない。ヒーター開発に取り組みつつ、生活費を確保するために商工会議所に融資の相談へ足を運ぶ。研究設備どころか家賃の工面すらままならない時期もあった。「アイデアはあるが、カネはない」日々そう痛感させられたと振り返る。
しかし「困っている人がいるなら駆けつける。電話は24時間応える。」それが長谷川のやり方だった。風呂場だろうがトイレだろうが、いつでも電話を取り、依頼があれば現場に向かい、試験的に製品を設置する。その場で不具合が見つかれば、徹夜で構造を練り直す。スイッチの誤作動はセンサー設定の問題か、雪の性質か、温度差か。ひたすらトライ&エラーを繰り返しながらノウハウを積み上げていった。
印象深いエピソードを問うと「お金がないまま研究を続けたことが一番きつかった」と苦笑いを浮かべながら口にする。「あの頃は電話代すら惜しくて、でもお客様の電話は絶対に出なきゃいけないし、どうにかしなきゃという思いで毎日生きていましたよね。」という言葉には、どこか懐かしさすら感じてしまう。生活資金のめどが立たないどころか、試作品は失敗だらけ。それでも少しずつコンクリート中にヒーターを通す技術を磨き、ロードヒーティングを現実にしていった。大手ハウスメーカーと提携し、次々と施工依頼が舞い込み始めたのは、こうした地道な努力が実を結んだからこそだろう。
さらに2010年代に入り、小型風力発電のブームが到来。海外製の風車が魅力的な売電価格とともに市場を席巻した。しかし、思わぬ故障やメンテナンス不足で全国的にトラブルが多発する。製造元が倒産し、アフターサポートが消え去ったケースも頻発した。そんな状況で、長谷川は青森で立ち上がる。使う人が困っているのなら何とかしようとメーカーに直接問い合わせ、部品の調達方法を探り、現場のメンテや改良案を提示し始めた。「自分がやらねば、誰が助けるんだ。」その義侠心めいた姿勢は、結果的に全国各地の小型風力発電ユーザーを救う一手となった。
究極の地産地消を青森から
歌人・若山牧水のあまりにも有名な短歌が胸をよぎる。
「幾山河(いくやまかわ)越えさりゆかば さびしさの果てなむ国ぞ 今日も旅ゆく」
いくつもの山や川を越えていけば、その先には果てしない“さびしさ”が広がっているかもしれない。それでも旅は続く。若山牧水は自然の風景のなかで自らの在り方を見つめ、孤独とロマンを抱きしめるようにして歌を詠んだ。旅はいつだって孤独だ。だが、前に進まなければ見えない景色がある。
長谷川と若山牧水の共通点は、その“行動する叙情”にあると言えるのではないか、とさえ思う。詩や短歌は一見、静のイメージを伴うが、若山牧水は日本各地を旅しながら感性を研ぎ澄まし、歌を生み続けた“動”の歌人だった。同じように長谷川は現場を飛び回りながら、新しい可能性を探り続ける。“動き”のなかで魂が磨かれ、そこから見えてくる地元・自然・人間のリアルを製品づくりや施工管理に反映していくのだ。そこには計算づくの戦略ではなく、どこまでも現場主義を貫く強い意志がある。
長谷川の人生にもまた、何度も越えなければならない山河があった。資金難、技術の壁、家族の心配、地域社会からの疑問。それらをひとつずつ踏み越えるたび、青森の風は彼を試すように吹きつける。しかし、挑戦は途絶えない。
今の彼の焦点は「地産地消エネルギー」の究極形だという。雪深い冬こそ風が吹き荒れる。ならばその風で発電し、自分の家のロードヒーティングに回そう、あるいは蓄電池を併用して災害時に役立てよう…こうした一連の流れをスタイリッシュに、かつ安価に実現するために動いている。五所川原市と連携して工業団地向けの自家発電システムを構想中であり、ペロブスカイト発電シートの研究や蓄電池の最適利用も含めて、青森発の「エネルギー革新」に挑む。かつては無我夢中で電話を取り、雪かきスコップを握りしめた若者が、いまや南極観測隊に風車を届ける技術協力にまで関わる。何やら物語めいたスケールの広がりを感じずにはいられない。
自らの熱で風を起せ
「地産地消で次の世代にバトンを渡す」。それが長谷川の揺るぎないモットーだ。大きな企業が新技術を押しつけても、地域社会に馴染まなければ意味をなさない。雪と風と共存しながら培ってきた経験と知識を、「次の世代」へ届けたい。誰もが大都市に出ていってしまう流れのなか、青森から“再エネ世界一”を目指す、そんな夢物語を語る彼の言葉にはどこか地面に足のついたリアリティがある。実際、夜中でも電話を取っていた男の言葉なのだから、まったくに荒唐無稽な理想ではない気がするのだ。
最後に長谷川は若者へメッセージを贈る。「とにかく動いてみること。立派な施設がなくても、研究が紙一枚でも、アイデアがあればやれることはある。失敗なんて当たり前。その先にしか見えない景色があるんです。」ひたすら実践を重ね、地域の課題に自ら突っ込んでいった男だからこそ、この言葉には説得力がある。大きな風車だけが未来を作るのではなく、小さなブレードの回転からでも地域は変わりうる。幾山河を越える勇気さえあれば、きっと遠くの“さびしさ”も、新しい始まりのサインになるだろう。
大地が陽光を浴びて温められた空気は膨張して上昇し、冷えた空気がその跡を埋めようと流れ込む。この気圧差こそが風の源泉だ。まるで大地が呼吸するように、季節や地形が紡ぎ出す風は地域に多彩な表情を与える。青森の厳しい吹雪や海からの潮風も、すべては地球の鼓動に呼応して生まれるもの。だからこそ、その風を味方につければ、新たな挑戦の扉が開かれるのだ。
長谷川は、今日も青森の地で旅を続けている。いくつもの風を、味方につけながら。