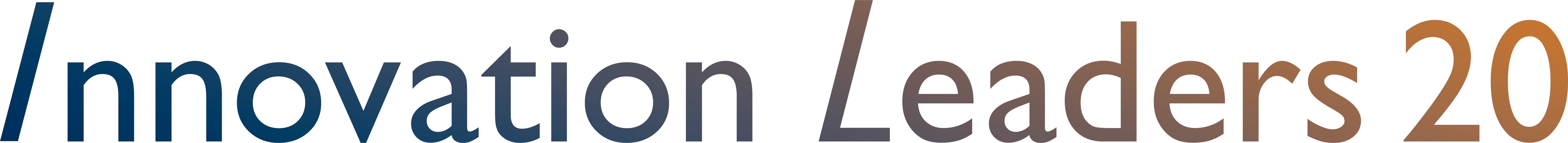自然・文化・課題の宝庫、十和田市
青森県十和田市。四季折々の美しい風景と、雄大な自然に囲まれたこの街は、奥入瀬渓流や十和田湖といった観光資源に恵まれ、多くの旅人を魅了し続けてきた。古くは馬の生産地として栄え「馬のまち」としての誇りを持ち続けながら、農業や酪農の発展にも力を入れてきた歴史ある地域である。現在では、草間彌生やロン・ミュエクといった名だたる芸術家の作品を所蔵している十和田市現代美術館などの文化施設が注目を集め、新たな観光スポットとしても発展を遂げている。しかし、一方で人口減少や空き家問題などの社会課題にも直面しており、まさに今、都市の再生と持続的な発展が求められている市でもある。
こうした課題を前に、持続的な発展を遂げるために地域に根ざした挑戦を続ける男がいる。有限会社橋場不動産の代表、橋場祐太だ。彼は不動産業の枠にとらわれず、新たな価値を創造し、地域社会に貢献し続けている。
事務所に席はなかった
橋場が不動産業に身を投じた背景には、紆余曲折があった。もともとは司法試験に挑戦し、弁護士を目指していたと語る橋場。大学院まで進学し、法の世界に身を置こうと奮闘していたものの、試験に三度挑んだ末に不合格。司法の世界ではなく、家業である不動産業を通じて人を助ける道があるのではないか。そう考え、橋場不動産に入社する決意を固める。
しかし家業に戻ったとはいえ、最初から順風満帆だったわけではない。入社したタイミングでは事務所はすでにパンパン、自分の席すら置くことができない状態だった。社屋のとなりにある喫茶店の片隅で仕事を始めるところからのスタートだったという。とはいえ、PCがあれば仕事はできた。一方で紙と電話、FAXが当たり前だった社内環境に違和感を覚えた橋場は、ITを駆使した業務改善を推し進める。しかし、伝統的なやり方に慣れている古参社員との軋轢も生まれた。スプレッドシートでの共同編集を導入した際も、社内から反発があったが、彼は諦めなかった。
「変革には時間がかかります。会社として痛みも伴うかもしれません。しかしやるべきことを貫けば、結果は必ずついてきます。」そう語る橋場の信念は揺るがなかった。結果として社内のデジタル化が進み、業務の効率は飛躍的に向上。社内そして顧客とのやり取りも電話からチャットへ移行し、無駄な業務が削減された。さらに、行政書士の資格を取得し、不動産相続や空き家問題にも対応できるように。地域の課題を解決するために、できることを一つひとつ増やしていったのだ。
やるなら全部オンラインで
現在、橋場は完全非対面の契約システムを構築し、顧客がスマホ一つで物件を契約できる仕組みを作り上げた。遠方からでも契約できるため、十和田市の不動産市場にも新たな可能性が生まれている。
だが、それだけでは終わらない。彼は今、空き家問題に真正面から向き合っている。地方都市では、親から相続した不動産を持て余し、放置するケースが後を絶たない。これらの物件が管理されずに放置されると地域の価値は下がり、さらなる人口流出を招く。そこで彼は「空き家管理サービス」を立ち上げ、オーナーに代わって物件のメンテナンスを行う仕組みを構築。さらに自治体とも協力し、再活用のためのマッチング支援を進めている。全国的にも問題視されるこの課題に対し、橋場は行政や他の専門家と連携しながら、持続可能な解決策を模索しているのだ。
チャンスはここにある
「人生即努力、努力即幸福」と説いた本多静六は「貯蓄の神様」とも称され、日本の都市計画や森林保全に多大な貢献を果たしてきた。倹約と投資を徹底し、その資産を社会のために役立てることに生涯を捧げた。自らの資産を活用し、公共のために公園の整備を進め、日本各地の都市計画に尽力したことで、現代においても彼のその功績は語り継がれている。彼の哲学は単なる個人の利益追求ではなく、社会全体の繁栄を見据えたものだった。未来のために資産を形成し、持続可能な発展を促す考え方は、現代のまちづくりにも通じるものである。
橋場の取り組みも、まさにこの精神と一致するといえよう。彼は、ただ不動産を売買・賃貸するだけでなく、十和田市という地域に価値を還元しようとしている。不動産のデジタル化、空き家対策、賃貸契約の完全オンライン化といった手法を通じて、地域住民が安心して暮らせる環境を整えようとしている。彼の視点は短期的な利益ではなく、長期的な地域発展を見据えたものに他ならない。情報技術が発展し、どこにいても知識を得られる時代。だからこそ、「地方だからできない」と考えるのではなく「地方だからこそできること」を見つけることが大切だ。特に十和田のような地方都市には、まだ手がつけられていない課題や未開拓の領域が多く残っている。そこには、新しいビジネスや働き方を生み出せる可能性がある。
ただし、変化を起こす際に忘れてはいけないのは、変化に対する反発があることを前提に、うまく伝えていくことだ。橋場自身も社内のIT化を進める中で、旧来のやり方にこだわる人々との衝突を経験した。しかし、結果を出しながら徐々に受け入れてもらうことで、業務の効率化を成功させた。新しいことを始めるときは周囲の反応を無視せず、どうすれば納得してもらえるのかを考えながら進めることも大事なのだ。
橋場自身、司法試験に挑みながらも道を変え、不動産業という新たなフィールドで挑戦を続けてきた。失敗を乗り越えることが、成長への大きな糧となる。どんな道を選んでも、自分の手で未来を切り拓く意志さえあれば、道は必ず開ける。橋場祐太の生き様が、その証明なのだ。「挑戦することを恐れてはいけないとつねに心がけています。たとえ失敗しても、挑戦しなければ新しい価値は生まれないですから。もちろん最初は思い通りにいかないことが多いかもしれない。しかし、一歩踏み出したその先に、まさに自分だけの道が開けると思っています。今の時代、一度外に出た人も、今ここにいる人も、情報を活かして挑戦できるのが十和田市ではないでしょうか。社会の課題は、誰かが解決しなければならないもの。ならば、自分がその役割を担うのも悪くないと思っています。問題を避けるのではなく、正面から向き合い、解決策を見つけることが大切ですから。街を良くするために、やるべきことはありますね、本当にたくさん…笑。」
挑戦し続ける者だけが、新しい時代を創ることができる。