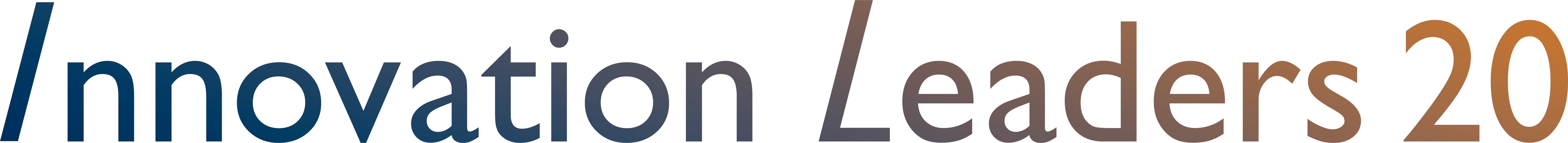青森が誇る光の彫刻師
ココ・シャネルは「流れに逆らう者こそが川の本流をつくる」と語った。彼女の生き様は、固定観念に縛られず、自らの道を切り拓く女性の姿そのものだった。その精神を受け継ぐかのように、青森の地で一人の女性が運命を変えようとしていた。北村麻子、日本初の女性ねぶた師。男の世界とされてきたこの伝統芸術に挑み、ねぶたの灯りをさらに鮮烈に輝かせた女性だ。
ねぶたが灯る夏の夜、浮かび上がる巨大な灯籠の背後には、血の通った人間の情熱と時間とが凝縮されている。紙と竹の骨組みが作り上げるその独特の立体造形は、まるで巨大な生物のように脈打ち、見る者の心を鷲掴みにする。青森が世界に誇るこの伝統芸能を支えるねぶた師という存在は、彼らの作品が夜空を彩る刹那にのみ注目されがちだが、実際には長い時間と想像力、そして繰り返しの試行錯誤を要する孤独な戦いに身を置いている。北村麻子は、数少ない女性ねぶた師としてその道を極めてきたアーティストだと言えよう。
彼女が創り出す作品には、青森の土の匂いと生命力が溶け込み、同時に繊細な女性の視点が織り込まれる。挑戦する心を常に絶やさず、素材や色彩の扱いに独自の美意識を滲ませながら、伝統と革新をしなやかに結び合わせる。その姿勢は、ねぶた師という肩書きにとどまらず、芸術家としての無限の可能性を感じさせる。
衝撃を受けた20代
ねぶたとは、青森の魂そのものである。夜空を焦がすほどの熱狂、火花のように舞う囃子の音、そして勇壮に跳ねる観衆。それらを統べるのが、巨大なねぶたの姿だ。戦国武将や伝説の神々、神話の英雄たちをモチーフにしたこの灯篭は、まさに生きているかのように街を駆け抜ける。ねぶた師とは、その圧倒的な存在感を創り上げる職人のことである。しかし、伝統の世界に女性の居場所はないとされてきた。
北村麻子は、そんな「暗黙の掟」に抗うこととなった。彼女が幼少のころから見つめ続けたのは、ねぶたの名匠である父・北村隆の背中だった。しかし、それはあくまで「遠いもの」として映っていた。女性がねぶたをつくるなど、誰も考えもしなかった。彼女自身ですら。
高校を卒業した彼女は、すぐにねぶたの道へ進んだわけではなかった。最初は販売業や一般企業のOLとして働き、社会の現実と向き合う日々を送る。だが、その間にも「自分はこのままでいいのか」という漠然とした疑問が彼女を苦しめ続けた。そして20代半ば、ある年のねぶた祭りで父の作品を目にした瞬間、すべてが変わる。「私も、これをつくりたい。」電撃のような衝動が彼女の人生を決定づけた。
「長い」道のり
ねぶたの世界は、力の世界だ。巨大な骨組みを組み、紙を貼り、絵を描き、そして魂を吹き込む。そのすべてが、腕力と体力、技術を求めるものだった。最初から周囲の反応は冷ややかだった。「女にできるわけがない」「重いものも持てないだろう」「すぐに辞めるだろう」そんな言葉が彼女の耳に突き刺さる。しかし、彼女は一つひとつの疑念を実力で覆していく。
膨大な量の下絵制作、骨組みの組み立て、紙貼り、彩色という地道かつ膨大な作業が続く。しかも、ねぶた作りのスケジュールはほとんどが“締め切りとの闘い”だ。祭り当日に間に合わなければ作品が日の目を見ることはない。「時間が足りなければ眠る時間を削るしかない。だけど、そこに人間の情熱や創造性がすべて詰まっている」と、北村は当時を振り返りながら語る。
そして初めて手掛けた大型ねぶた「琢鹿の戦い」で優秀制作者賞を受賞。だが、それですら「女性だから贔屓されたのではないか」と陰口を叩かれることとなる。「本当は父が作っているんじゃないか」とすら言われた。だが、彼女は動じなかった。作品をつくり続けることで、まさに実力で批判を黙らせていった。
それから10年以上が経ち、今や彼女はねぶた界の第一線で戦い続けている。彼女のねぶたは力強さと繊細さを併せ持ち、観る者の心を掴む。「紅葉狩」「神武東征」「雷公と電母」。彼女の手がけたねぶたは数々の賞を受賞し、その感性と技術を証明している。
新しい伝統をつくりたい
現在、北村麻子は青森市内を拠点としながら、複数のプロジェクトを同時進行で進めている。例えば近年では企業や地方自治体からのオファーに応え、PRやイベントで活用できるミニねぶたの制作も手がけている。本来、大型のねぶたは青森の夏祭りという季節的な枠組みにとどまりがちだが、北村の試みはその枠を超えて、ねぶたを通年のコンテンツとして展開する可能性を示唆している。例えばショッピングモールや観光キャンペーンの一環でミニねぶたを展示したりと、ねぶたの新たな魅力を発信している。
そして彼女の挑戦はねぶた制作だけにとどまらない。ねぶた師としての道を切り拓いただけでなく、SNSを活用し、新たな人材をこの世界へと引き寄せ続けている。インスタグラムでの発信を通じて「ねぶたを作りたい」と全国から人々が集まり、人材不足に悩んでいた現場を活性化させた。「以前は鹿児島の奄美大島から応募が来たこともありましたね…さすがにどうしようかと思いました(笑)」と、北村は朗らかに語る。
「NEBUTA from AOMORI」へ
そして彼女は、ねぶたを世界へと広げようとしている。父がかつてイギリスの大英博物館で制作を行ったように、彼女もまた世界にねぶたを持ち込み、新たな歴史を刻もうとしている。ねぶたは青森だけのものではない。世界の人々に、その熱狂と美しさを伝えることができるものなのだ。「女性だからこそ見える角度がある。伝統って、本質を守りながらも、時代に合わせて変化していくからこそ生き残るんじゃないでしょうか」。北村の言葉には、彼女が積み重ねてきた知識と経験、そして柔軟な挑戦心が滲む。
そして北村は若者たちにこう語る。「挑戦することを恐れないでほしい。実は私は、20代半ばまで自分が本当にやりたいことが何かまったく分からなかったんです。でも、ねぶたと出会い、自分の中に眠っていた情熱を見つけた。だから少しでも興味を持ったことがあれば、その感性にしたがって、恐れず飛び込んでみてほしい。自分の道を信じることが、未来を切り開く鍵になるんです。」
これまで築いてきた技術をさらに磨き上げる一方で、青森という土地の力強い文化を世界に向けて発信する…その二つを同時に叶えようとする北村麻子の姿勢は、ねぶた師という枠を超えた“アーティスト”そのものである。彼女が導く未来のねぶたは、祭りの夜空だけでなく、世界中の多彩な舞台をも眩いばかりに照らし出すに違いない。