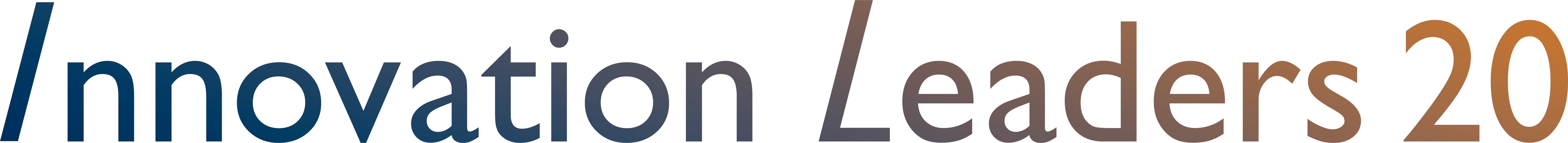伝統と革新の「バランス」
こぎん刺しは、単なる装飾ではない。江戸時代、津軽地方の農民たちは厳しい寒さと経済的制約の中で、麻布しか着ることを許されなかった。目の粗い麻布は保温性に乏しく、そこで生まれたのが、木綿の糸を用いた「刺し子」だった。奇数目を数えて施される刺し子は、布を補強し、保温性を高めるという実用性を持ちながらも、やがて独自の美意識へと昇華した。こうして生まれた「津軽こぎん刺し」は、日本三大刺し子の一つとして確立される。
こぎん刺しには三つの主要な種類がある。「東こぎん」は太めの粗い麻糸を使い、大胆な模様が特徴。「西こぎん」は苧麻(からむし)の細い糸を使用し、緻密な模様を描くことで知られる。「三縞こぎん」は、金木町周辺で発展し、鮮やかな三本の縞模様が特徴だ。これらのこぎん刺しには、「モドコ」と呼ばれる伝統的な幾何学模様が用いられ、現在40種類ほどが存在している。
この伝統を継承し続けてきたのが、弘前こぎん研究所である。1942年、地域産業の発展を目的として誕生し、60年代には「こぎん刺し」を中心とした事業へと転換。現在に至るまで、手仕事の技術を守りながらも、新たな挑戦を続けている。
杉本貞吉が戦後の混乱の中で日本生命の再建を成し遂げた話を思い出す。徹底した合理化と強靭な経営哲学を持ち、危機を乗り越えた男。だが、その成功の裏には、伝統と革新の絶妙なバランスがあった。時代に応じて変化しながらも、決して本質を見失わない。その姿勢こそ、今日の「弘前こぎん研究所」会長の成田貞治に重なる。
連鎖倒産の危機
成田貞治は1949年、青森県弘前市に生まれた。電気工事の道に進んだが、1979年、父の要請により弘前こぎん研究所へ入社。最初は乗り気ではなかった。むしろ、地味で女性が多い職場に違和感すら抱いたという。「電気工事の現場では、男同士が喧嘩して酒を飲んで、それで終わり。でも、ここは全然違いました。」
しかし、次第に「こぎん刺し」の魅力に惹かれていく。初代所長の著作を熟読し、自らも針を持ち、刺し続けた。そして気がつけば45年。この間、経営の危機もあった。連鎖倒産の波に飲み込まれ、負債を15年かけて返済した。「もう潰すしかない」と何度も思ったが、最後の一線で踏みとどまったのは、「こぎん刺し」という文化を守り抜くという信念だった。
こぎん刺しの本質は「変化と継続のバランス」にある。かつては、紺地に白糸が基本だったが、現代では色とりどりの糸が使われるようになった。それを批判する声もあったが、成田は信じる道を進んだ。「ただ昔のままでは商売にならない。商売にならなければ伝統は廃れる。だからこそ、変化が必要なんだと感じました。」代表はゆっくりと言葉をならべていく。
新しい時代に即したデザインを取り入れながらも、弘前こぎん研究所がこだわるのは、手仕事の質だ。機械で量産する「こぎん風」の製品が市場に溢れる中、成田は決して妥協しない。「本物」のこぎん刺しは、機械には真似できない温もりと魂が宿る。だからこそ、研究所では現在も100名近い職人たちが、一針一針を手で刺している。
こぎん刺しの本質
伝統工芸の最大の課題は、継承者の確保だ。成田も75歳となり、娘やその夫が経営を担い始めた。しかし、次世代へと技術を継ぐことは容易ではない。だからこそ、産・学・官の連携を強化し、学校教育にもこぎん刺しを取り入れる試みを進めている。
さらに、「津軽こぎん刺し」を地域ブランドとして確立し、全国・世界へと発信する計画も進行中だ。成田自身は「海外進出には興味がない」と言うが、それは「日本の市場で十分に価値を伝えられる」という自信の表れでもある。
彼の座右の銘は「十人十色」。それは多様性を尊重し、伝統の中にも新しい風を取り入れる柔軟性を象徴している。例えば、かつてのこぎん刺しは紺地に白糸が基本だったが、今ではカラフルな色彩が加わり、より多くの人に受け入れられるデザインへと進化した。とはいえ、弘前こぎん研究所が重視するのは、「手仕事の魂」だ。機械生産が進む中で、成田は「手刺しの温もりこそが、こぎん刺しの本質である」と断言する。
伝統とは、変わり続けること
「AIの時代になろうが、どれだけ技術が進歩しようが、人の手が生み出す価値は変わらない」その言葉には、伝統に生きる者の矜持がある。「目標がないなんて そんなの当たり前だと思ってるんです。私だって最初はやる気なんてなかった。でも、続けるうちに見えてくるものがあります。」彼の人生は、その言葉を証明している。
こぎん刺しに興味がなく、いつ辞めてもいいと思っていた男が、今やその第一人者として道を切り拓いてきた。やりたいことがなくてもいい。ただ、何かを続けてみる。そこから、新しい道が生まれることもあるのだ。
弘前こぎん研究所は、単なる伝統工芸の会社ではない。それは、「生きる知恵」と「ものづくりの魂」を次世代へと繋ぐ場だ。成田貞治が守り、築いてきた道は、これからも続いていく。
「伝統とは、変わり続けること」その信念のもと、弘前こぎん研究所は未来へ向かって歩み続ける。