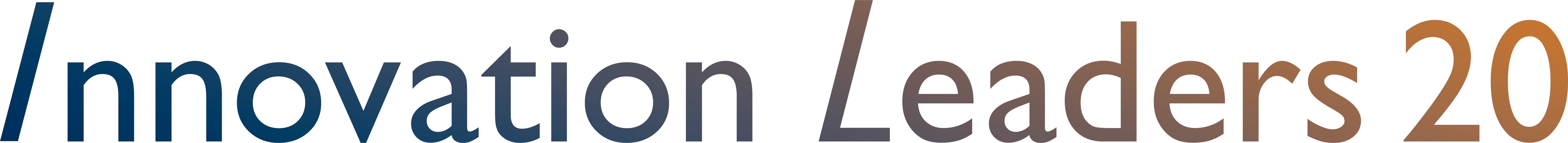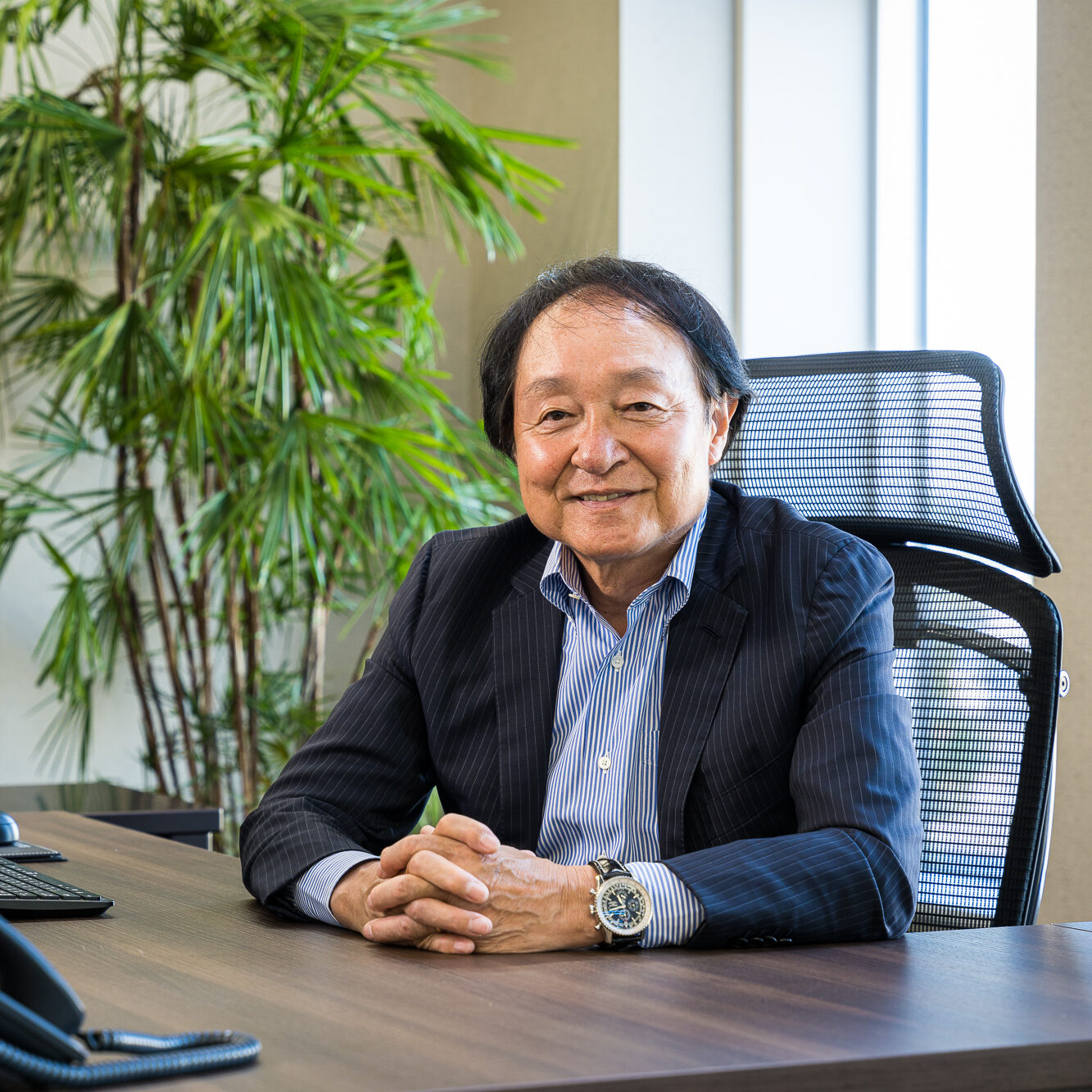東北全域を支える電設資材の要
日本の最北端に位置する本州の玄関口であり、四季折々の豊かな自然に囲まれた地、青森市。冬の厳しい寒さと、夏の短い爽やかな気候が特徴的であり、その自然環境が市民の生活や産業にも大きな影響を与えている。また文化的にも豊かであり、ねぶた祭りなどの伝統行事が全国的に有名だ。これらは地域のコミュニティを強く結びつけるとともに、観光資源としても高い価値を持っている。そんな東北の厳しい寒さのなかにあって、地域の電設資材業界を支え続ける企業がある。
東和電材株式会社。青森を拠点に、東日本一円へと事業を展開し、時代の変化とともに進化し続けるこの会社を率いるのが、代表の榊美樹だ。1956年の創業以来、電設資材の製造・販売を中核とし、青森の地で成長を続けてきた東和電材。創業者である榊の父のもとで、会社は少しずつ規模を拡大し、電気工事業界における確固たる地位を築いていった。
今、代表を務めている榊の経営哲学は、一見すると実直で堅実なものに見える。しかし、その本質はむしろ、挑戦と変革の連続という表現がふさわしい。彼の経営スタイルは「企業とは生き物であり、成長し続けなければならない」という信念に裏打ちされている。その視線は、過去の成功に甘んじることなく、つねに未来を見据えている。
しかし、榊がこの企業の舵取りを担うまでの道のりは、決して平坦なものではなかった。
“2年”の覚悟
榊は青森大学卒業後、東京へ渡り就職する。就職したのは主に自動車部品を扱う矢崎総業株式会社。特に自動車用ワイヤーハーネスは世界首位を誇るなど、今も世界的に活躍を続けている企業である。そこでは日本経済の中心地である丸の内や大手町での営業を経験し、電設業界の本質を肌で感じる日々を送った。このとき、彼が未来に描くべき経営者としての基盤が形作られたという。
だが、運命は思わぬ形で彼を青森へと呼び戻す。31歳のとき、家業である東和電材への入社を決意する。最初から経営の中枢にいたわけではない。彼は営業・管理・財務などすべての部門を社員から経験し、約10年の歳月をかけてある種の「帝王学」を学ぶこととなる。会社のあらゆる部門を知ることで、自身が経営者としてどうあるべきかを深く考えたと榊は語る。
その過程で、彼は幾度も岐路に立たされた。特に、38歳のとき、父から突然「社長を継いでくれ」と告げられたそのときには、覚悟ができていないと判断し、「あと2年くれないか」と猶予を求めた。そして確保できたこの2年間は、彼にとって極めて密度の濃い時間だった。
研修、国内外の視察、経営者としての哲学の確立…榊がこの2年間で学んだのはただの知識ではない。企業が生き延びるための本質的な視点そのものであった。経営は数字だけでなく、人、文化、地域社会との関係性によって成り立つものだと痛感したのである。青森という土地で生き続ける企業として、何を大切にし、どのようなビジョンを持つべきかを深く考え、その想いを社内に浸透させていく決意を固めた。この決意こそが、後の東和電材の飛躍へとつながっていったのである。
そして、あらゆる準備を整え、40歳で正式に代表取締役社長に就任する。
企業に必要不可欠な「ビジョン」
榊の経営思想には一つの特徴がある。それは「長期的な視点」だ。彼は短期的な利益を求めるのではなく、10年、20年先を見据えた経営を続けている。
彼は言う。「経営は1日1日の積み重ねです。でも、企業としてどこを目指すのか、社員が同じ方向を向くためには、しっかりとしたビジョンが必要不可欠です。」彼が語るその「ビジョン」とは、単なる目標設定ではない。それは企業が社会に対して果たすべき使命を意味するのだ。
榊にとって、企業とは単に利益を追求する組織ではなく、社会の一員として責任を果たす存在だという。彼は「経営とは社会と共に歩むもの」という考えのもと、長年にわたり企業の成長とともに地域社会への貢献を続けてきた。彼にとって、社員が誇りを持てる会社であることはもちろん、その会社が属する地域が繁栄し、豊かであることもまた重要な要素なのだ。
最近では、SDGsの視点を経営に取り入れ、エネルギー・環境・防災に関連する事業にも積極的に参画。気候変動への対応や省エネルギー設備の導入推進など、環境負荷を軽減する取り組みを進めるとともに、災害時に迅速な電力供給が可能となるインフラ整備にも関与している。さらに、地元のジュニアサッカー支援を通じて、次世代の育成にも力を入れている。スポーツを通じた青少年の教育や地域コミュニティの活性化に貢献することで、長期的な地域社会の発展を支えていきたいという思いがある。
「企業とは単に売上を上げる場所ではなく、未来を創造する場である」という榊の言葉には、彼の経営に対する深い哲学がある。事業を通じて社会を支え、人々の暮らしをより良くするという理念が、東和電材の活動の根幹を成しているのだ。
経営とは未来をつくること
アメリカの19世紀の思想家ヘンリー・デイヴィッド・ソローは「所有せず豊かに生きる」という哲学を提唱し、自然の中で質素に暮らすことを選んだ。しかし、彼の本質はただの隠遁などではない。「自分の人生をどうコントロールするか」にあったのだ。彼は単に物質的な豊かさを捨てることで精神的な充実を得ようとしたのではなく、むしろ「何を持ち、何を持たないか」を意識的に選択しながら生きることの重要性を説いた。これは単なる自己満足ではなく、社会とどう関わるか、どのように自分の役割を果たすかを考えるための手段だった。
榊もまた、経営の世界において同じような視点を持つ。彼にとって企業は単なる利益を生み出す機関ではなく、地域社会の一員としてどのように役立つかを考え続ける存在である。だからこそ、短期的な売上や市場シェアに執着するのではなく、長期的なビジョンを持ち、社員や地域とともに成長することを大切にしている。
「会社経営は、ある意味で自己の生き方を決めることと同じだ」と榊は語る。「何を優先し、何を犠牲にするのか。短期的な成功に満足するのか、それとも未来を見据えて持続可能な道を歩むのか。これは、個人の生き方と企業のあり方が交差する瞬間だ。」
「経営とは、未来をつくること」…榊の人生は、まさにこの言葉に集約される。彼は過去の成功に満足することなく、つねに未来へと目を向けている。その背中を追う社員たちがいる限り、東和電材はこれからも地域とともに歩み続けるのだ。