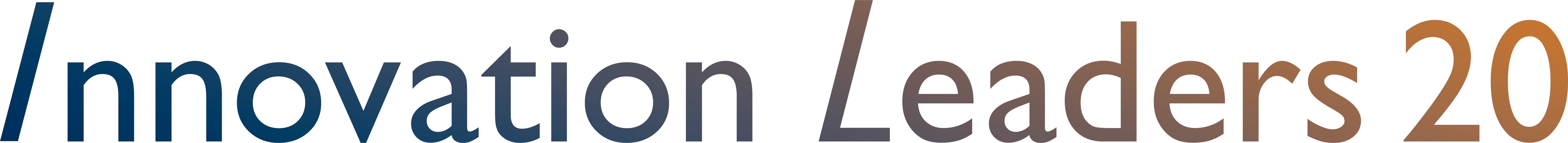空間は語る
青森県十和田市。奥入瀬渓流や十和田湖といった美しい自然に程近く、田園風景が四季折々の表情を見せるこの地は、昔から人々の営みと深く結びついてきた。明治時代以降、馬産地として栄えた歴史を持ちながら、現在では十和田市現代美術館をはじめとする芸術活動も盛んであり、アートと自然が共存する独特の魅力を持つ地域だ。そんな十和田で、杉山は土地に根づく建築のあり方を模索し続けている。彼の手がける建築は、その土地に息づく歴史や文化、人々の暮らしと、そこにある自然とのつながりを映し出す。彼の建築が風景の一部として馴染み、新たな価値を生み出していくことを、彼自身も大切にしている。
幼い頃から体感してきた青森の空気、土地、そして人々のくらしを、彼は建築というかたちで再構築してきた。とりわけ印象的なのは、伝統や地域文化の“根”をしっかりと踏まえながら、新しい要素を建築のなかに織り交ぜるその大胆さである。古い家屋の梁に触れたときのぬくもりと、現代の技術が可能にする洗練が同居する空間。そうして生み出される、やわらかながらはっとする空間は、まるでゆっくりとランプが灯り、物体の輪郭が浮かび上がるように、人々の営みをやさしく照らし出す。
彼は建築を通して空間を物語る。その語り口は、土地の記憶や人々の営みを包み込み、未来に向けた問いを投げかける。杉山貴亮。青森を舞台にこの建築家が綴る物語は、まだ序章が始まったばかりである。
“建築とは何か”見つめ直す日々
メキシコ人建築家のルイス・バラガン(1902–1988)。その美学はル・コルビュジエの影響を受けながらも、モダニズムの中に心の静寂を織り込む独自の世界を築いた。大胆な色彩と削ぎ落とした構成が空間に静寂を生み、壁や水面、陰影までも精緻に計算される。1980年にプリツカー賞を受賞し、その静かな衝撃は今なお世界を震わせ続ける。
杉山の建築との出会いは偶然だった。高校生の時にテレビで目にしたバラガン建築。その世界観に強烈に魅せられた杉山は進学先での専攻を建築学に決めた。大学で建築の専門知識を体系的に身につけ、建築の“構造”と“表現”を融合させる奥深さに惹き込まれていった。建築を学ぶ日々は新鮮な学びの連続で、これまでの人生で最も価値観を揺さぶられた時期だったという。知識を吸収し、挫折を重ね、成長していく。彼の中で建築は単なる職業ではなく、生き方そのものになっていった。
大学卒業後、東京や神戸でいくつかの設計事務所に勤め研鑽を積みつつ、自分はこの仕事を通して何を残せるのか、自問を繰り返す日々を送った。趣向の異なるクライアントに予算、スケジュール、建築基準法をはじめとした法令に関する知識や申請関係の手続き資料、調査・測量など、デザイン以外の業務をすべて問題なくこなしたうえで、感性に響く建築を作り上げるということが、本当に大変なことだと知った。設計事務所でのキャリアは単調なものではなく、大学卒業から10年あまりの間に、常識や自身が囚われていた価値観を見つめ直す機会を幾度も経験した。
なかでも広島県因島で、一連の健康食品会社のプロジェクトに携わった6年間は、彼にとって特別な時間だった。青森とは全く異なる、瀬戸内海に島々が浮かぶ自然の風景と、そこに繰り広げられる日常を捉えながら建築を構想していく仕事だった。環境が異なることで求められる建築のあり方が変わる部分もあれば、共通する部分もあり、建築のリアリティがひとつではないということを学んだ。また、業務の面では建築単体の設計だけでなくデザイン監修やプロジェクトマネジメントにも携わり、建築という仕事の全体像を見渡す視点を培った。「ひとつの仕事の中に多くの出会いがあり、変わるもの、変わらぬものを見た」と杉山は語る。6年間という時間は、彼に洞察力を教え、長期プロジェクトが完成した達成感は、彼に建築家としての自信を与えた。
「生きた空間」としての建築
創業にいたるまでに経験を積んできた中で、建築とは単なる物体のデザインの追求ではなく「人々の暮らしをかたちにあらわすこと」であることを学んだという杉山。「建築を必要とするクライアントの現実的な課題に応えることが最も大切です。」と語る彼が目指すのは、建築を『作品』としてではなく、『生きた空間』として機能させることだ。建築は人が生き、働き、休むための器であり、その器がどのような佇まいを持つかで、人の行動や気持ちは大きく変わる。もちろん、そのフォルムや素材使いなど、審美的な美しさもまた、器としての大切な機能のひとつである。
ただし、建築の美しさとは、建物単体の造形のみにあるのではなく、その場の空気、時間の流れ、使う人の記憶とともに醸成されるもの。たとえば、朝陽が差し込む窓辺、夏の涼やかな風が通る廊下、冬に家族が集まる温もりのある居間…これらはすべて、設計の意図によって生まれる。杉山の設計では、光と影のバランス、空間の広がりや圧縮、建物と周囲の関係性が繊細に計算されている。そうして、建築が『そこにあるべくして生まれた』ような空間を意志を持って生み出すことで、そこに住む人々が「この場所にいることの心地よさ」を意識して感じられるようになる。そうした空間での日常は、より“美しく”濃密な時間の流れを生む、と彼は信じている。
そして2018年11月、満を持して青森県十和田市にて独立。クライアントや職人をはじめ、協業者とのコミュニケーションを大切にする姿勢をモットーに、青森だからこそ生まれる建築を追求し始めた。若い感性と土地への愛着が融合した彼のデザインは、瞬く間に評判を呼び、仕事の幅も広がっていった。こうして「杉山貴亮」という名は、地元・青森に新しい風を送り込む建築家として、少しずつ確かな存在感を示しはじめたのである。
共通の価値観で特別な建築を
建築の仕事に取り組むうえで、杉山がもっとも大切にしているのは「全員が良いと思える建築を目指す」という視点だ。言い換えるならば、「一部の人だけが評価する建築」ではなく、「すべてのひとが自然と受け入れ、長く愛せる建築」を目指している。全員が良いと思うこと、それは妥協や中庸ではない。例えば、川沿いの家を設計するなら、その川のせせらぎをどう生かすかを考える。街中の喧騒から逃れるための静謐な空間を作る工夫も、彼の得意とするところだ。光や風といった、本能的に誰もが感じ取れる快適さにフォーカスし、その場にもともとある魅力を高めるための建築を考えるのだ。杉山の設計には、五感に訴えかける心地よさがある。日の光、風、緑、空。これらを意識することで、どんな人にも心地よい空間が生まれる。「建物のフォルムが美しく、使われる素材の手触りが良く、動線が適切であること。そういった細部への気配りが、誰にとっても心地よい空間を生み出す要素になります。」
自身の設計においてそれは、ただ美しさを追求するのではなく、環境や歴史、そしてそこに住む人々の想いを織り込んでいくことだ。『建築とは自然の一部であり、我々の営みもまた自然の一部です。建築は人の営みから生まれ、人の営みは建築から生まれます。』という彼の言葉は、すべての設計に息づいている。建築を通して生まれる「自然の記憶」そしてそれが次の世代へとつながり、さらに価値を持ち続けることこそが、本当に「全員が良いと思える建築」なのだと彼は信じている。
光や影、風や土や緑を愉しむ空間を志向することで、自然の中に佇む快楽を得られる建築を目指す。極端な形状や高価な素材を用いずとも、そうした“場を捉える視点”に依って設計することにより、多くのひとの理解を得られると信じている。だからこそ合同会社杉山建築設計事務所では、新築でもリノベーションにおいてでも、そこに住まう人や利用する人の動作や心理を思い描き、それらを包む光や色、空間を丁寧に紡いでいくアプローチを選んでいる。
また、建築は多くの人の協力によって成り立つ。クライアントだけでなく、行政機関、地域の住民、施工業者、職人など、多くの関係者が関わる。さらに、建築は10年後、20年後にも影響を与える存在だ。「だからこそ、一部の人だけでなく、できるだけ多くの人が納得し、愛着を持てる建築を作ることが重要です。」
環境は活かすもの
そしてもう一つ、彼が大切にしているのは「どんな場所でも魅力的な空間をつくることが可能である」という信念だ。それは理想論ではない。たとえ周囲を無機質なコンクリートに囲まれた狭小地であっても、採光や通風、視線の抜けを緻密に計算することで、驚くほど開放的な空間が生まれる。都市の喧騒の中にあっても、壁一枚の素材選びや、光の取り込み方一つで、そこに佇む人の感覚を変えることができる。建築は、どんな環境にあっても、工夫次第で心地よい空間を生み出せる。
どのような条件であっても、工夫することにチャレンジできるか否かが、建築の良し悪しを左右するとともに、そこにくらすひとの人生を左右する。「暗く湿った場所でも、光の取り入れ方や素材の工夫で心地よい空間は作れます。どんな条件でも、そこにしかない魅力を引き出すことが、建築の醍醐味です。」
夢には空間がある
杉山の仕事への向き合い方は、ひたすら真摯だ。大きく構えず、自分ができる範囲で確実にクライアントが喜ぶ仕事をすることに集中している。現在彼が手掛ける案件はすべて、これまでのクライアントからの紹介や知人を通しての出会いなど、等身大のコミュニティからつながっている。彼の建築を求める人の輪が徐々に広がっている証拠だ。
目の前のクライアントに精力を傾けるのと同時に、杉山は仕事を楽しみ、建築を楽しむことを多くのひとに伝えようとしている。そして大人が楽しく仕事をする姿を子どもたちに見せる。それが未来への贈り物になるという信念が彼にはある。「自分が携わった建築が地域に馴染み、子どもたちの記憶に残るようなものになれば、それ以上の喜びはありません。」
青森の豊かさは、決して特別なものではなく、当たり前の暮らしをどれだけ楽しみ、共有できるかで決まる。彼の創造はこれからも青森に新しい息吹をもたらし、地域に根づいた「夢」の空間が未来へと受け継がれていくだろう。その姿を見守りながら、私たちは、そこに生まれる次の物語を心待ちにしている。なぜなら、私たちが夢を思い描く時、そこには必ず空間があるのだから。
杉山建築設計事務所アトリエ 外観 photo Kuniya Oyamada
鳥曇 ギャラリー部分 photo Kuniya Oyamada
AURUM MISAWA ロビー部分 photo Kuniya Oyamada
杉山建築設計事務所アトリエ 内観 photo Takaaki Sugiyama